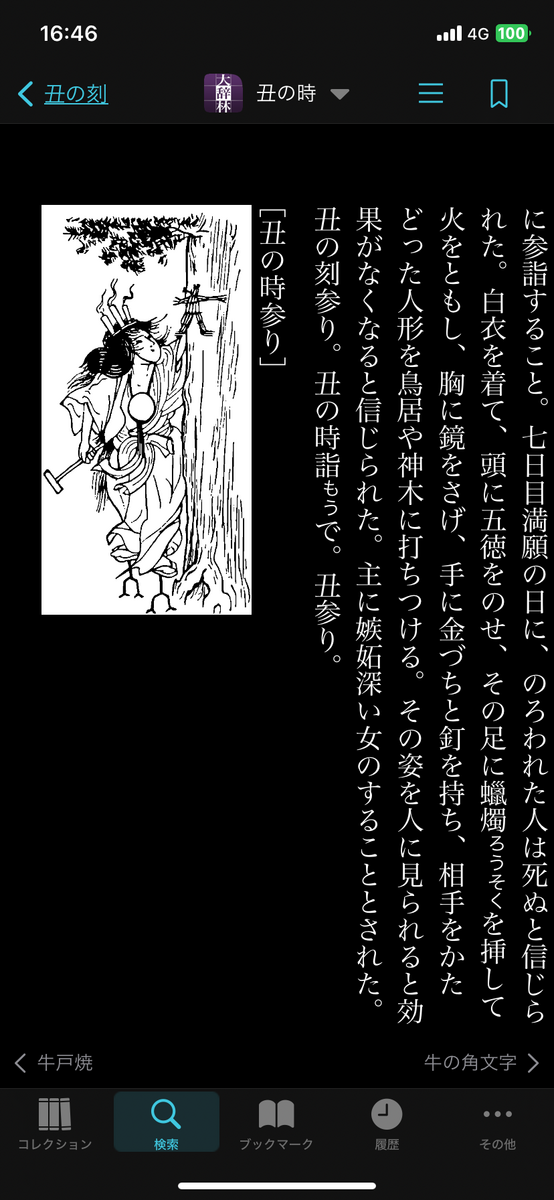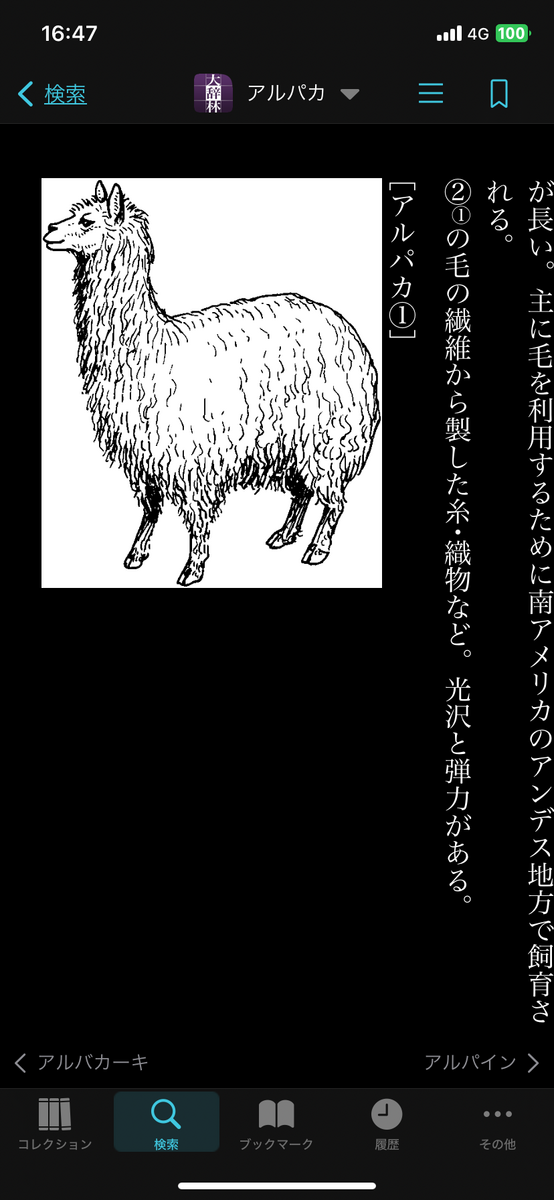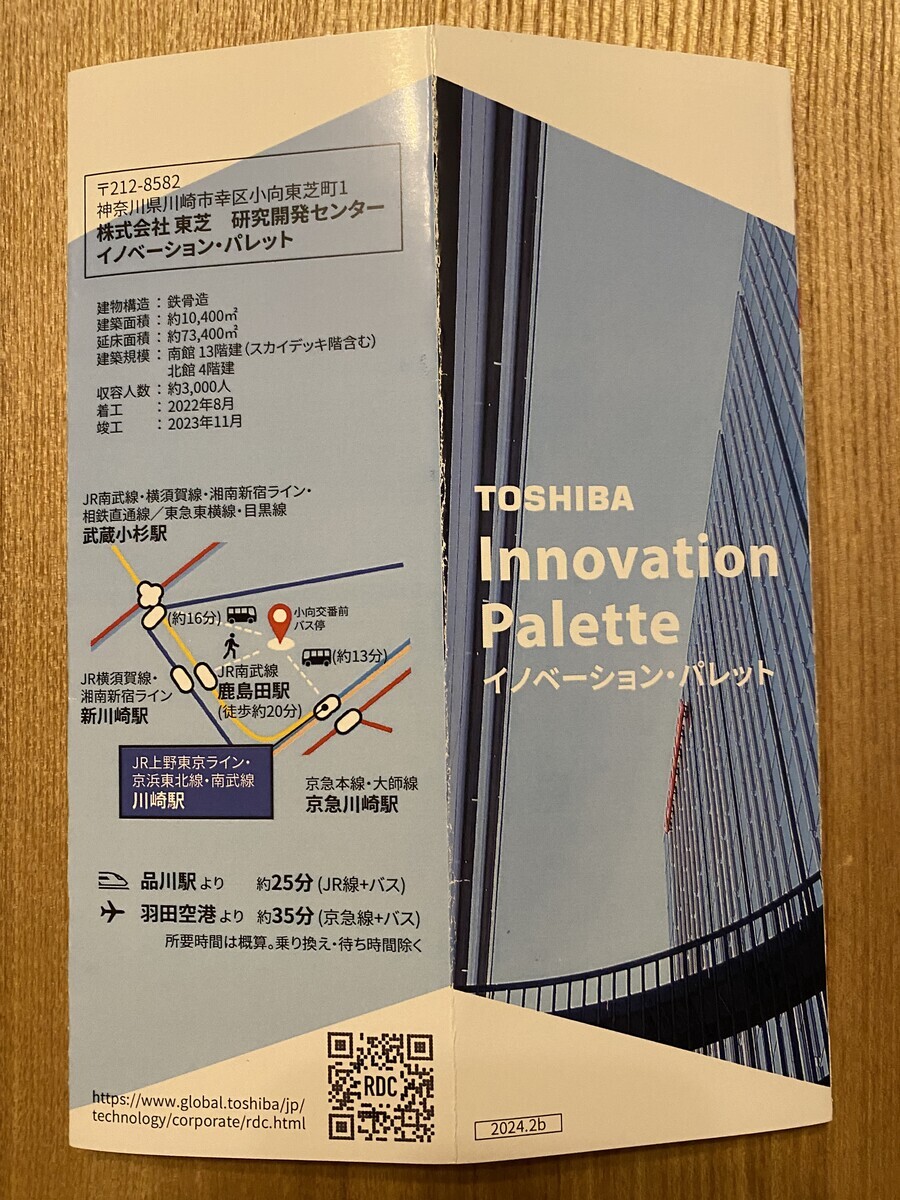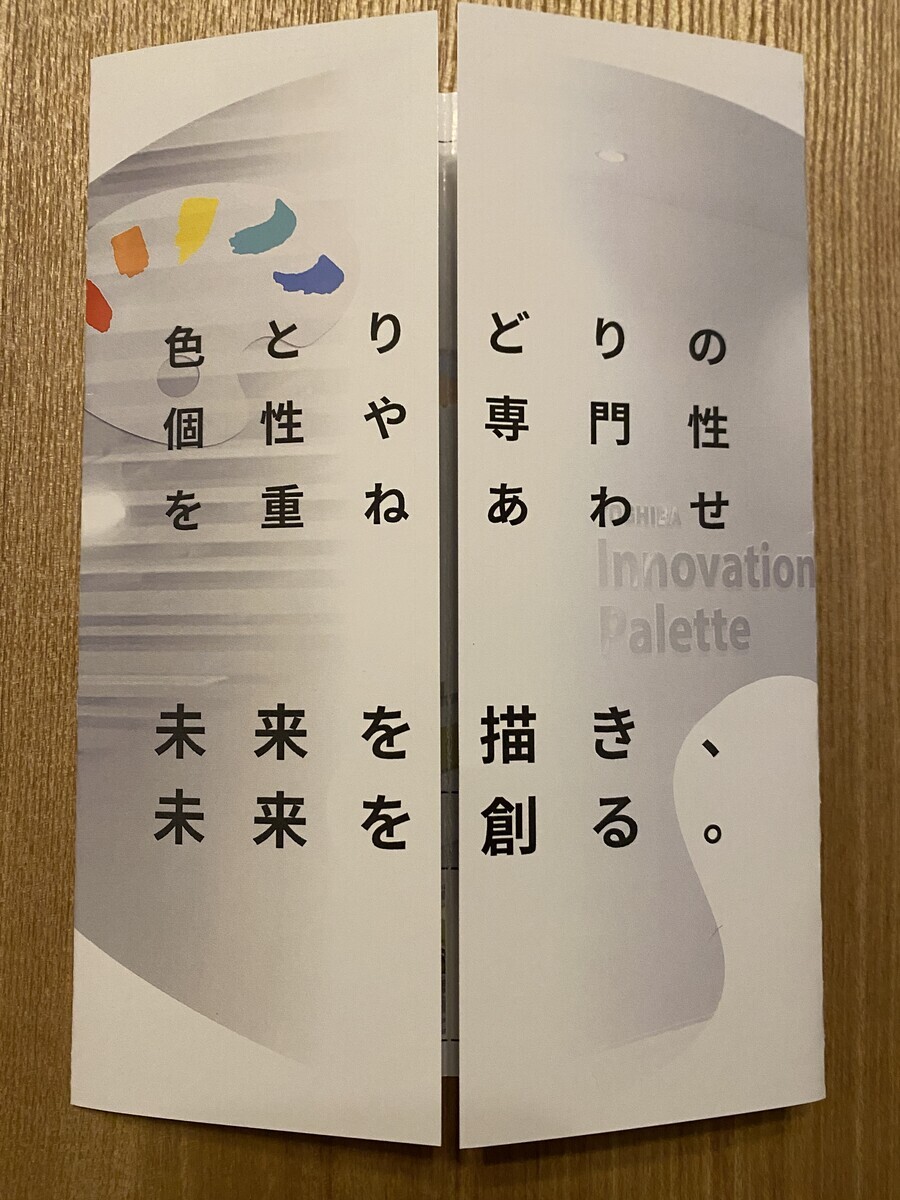老親を見舞った帰りに、練馬区立美術館で開催されている展覧会「生誕150年 池上秀畝―高精細画人―」を見る。池上秀畝(しゅうほ)という画家の名前は初めて聞くが、高精細画人という副題に惹かれたのである。


展覧会のサイト(チラシ)から概要を引用する:
池上秀畝(1874–1944)は、長野県上伊那郡高遠町(現在の伊那市)に生まれ、明治22年(1889)、本格的に絵を学ぶため上京。当時まだ無名だった荒木寛畝の最初の門人・内弟子となります。大正5年(1916)から3年連続で文展特選を受賞。また、帝展で無鑑査、審査員を務めるなど官展内の旧派を代表する画家として活躍しました。
同じく長野県出身で同い年の菱田春草(1874-1911)らが牽引した「新派」の日本画に比べ、秀畝らの「旧派」と呼ばれる作品は近年展覧会等で取り上げられることは少なく、その知名度は限られたものに過ぎませんでした。しかし、伝統に基づく旧派の画家たちは、会場芸術として当時の展覧会で評価されたことのみならず、屏風や建具に描かれた作品は屋敷や御殿を飾る装飾美術としても認められていました。特に秀畝は徹底した写生に基づく描写に、新派の画家たちが取り組んだ空気感の表現なども取り入れ、伝統に固執しない日本画表現を見せています。
本展は生誕150年にあたり、秀畝の人生と代表作をたどり、画歴の検証を行うと共に、あらたなる視点で「旧派」と呼ばれた画家にスポットを当てる展覧会です。
今回の展覧会が開催されている練馬区立美術館と長野県立美術館の学芸員が、池上秀畝と、その数々の作品を紹介している。
- 東京画壇の中では「旧派」に位置づけられる荒木寛畝の弟子
- 文展・帝展といった官展に毎回 2点出品して、3年連続で受賞している

ポスターやチラシに採用されているこの絵、《桃に青鸞図》はクジャクではなく青鸞(セイラン、鳳凰のモデルと言われている)を描いている。この絵だけでなく、多くの鳥を高細密に描いている。その写実性はなかなか凄い。

洋画と対比する中で日本画という概念が生まれた。『日本美術史』などの概説書で、近代日本画の歴史が語られる時には、フェロノサや岡倉天心をルーツとし、国際的に通用する日本画を求めて、朦朧体をはじめとする新しい試みを続けた「新派」が主に取り上げられるため、保守的な「旧派」の画家たちはあまり知られていない。この展覧会では、池上秀畝と同い年の新派のリーダー、菱田春草の絵と並べることで、その比較を行っている。
この展覧会を機に、日本画の「旧派」について少し学んだ。
古田亮『日本画とは何だったのか』は、新派・旧派を対比させつつ、近代日本画の変容の通史を描く、とても面白い近代日本画史論である。地方で受け入れられていた「旧派」の画家の一人として、池上秀畝が言及されている。
また草薙奈津子『日本画の歴史 近代篇』では、「忘れられた明治の日本画家たち」の一人として、池上秀畝の師匠である荒木寛畝(かんぽ)が「旧派」の重鎮(文展の審査員)として紹介されている。一時、洋画に転向して高橋由一に学んだ後、再び日本画に戻った画家である。東京美術学校を岡倉天心が追われた折に、連袂辞職した‿橋本雅邦の後任として、教授となっている。




















![舟を編む 通常版 [Blu-ray] 舟を編む 通常版 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61dhNVOvavL._SL500_.jpg)