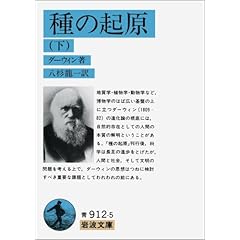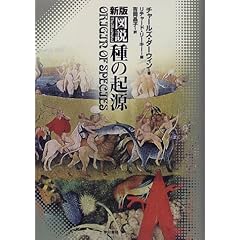今日2009年2月12日はダーウィン(Charles Darwin)生誕200年にあたり、また今年2009年は『種の起源』("On the Origin of Species"、岩波文庫〈上〉・〈下〉
)が発刊されて150年ということで、The Economist 誌が進化論を紹介している("Unfinished business")。
記事の中でまず興味を引くのは、国ごとに進化論をどのくらい受け入れているかを示す次のグラフである:
このグラフを見て、「神の存在を信じる」ことと、進化論を認めることとが負の相関にあるのがすぐに見て取れるが、記事ではさらに別の見方を紹介している。それは、食べものが豊富でヘルスケア・住宅がいきわたっている国ほど、神への信仰が薄いという見方である。淘汰圧の支配下にある社会ほど、信仰に重きを置き、進化論を否定する。
いずれにせよ進化論を受け入れないことには、現代科学はありえない。進化論は、生物学・医学にとどまらず、社会のいろいろな分野で影響を与えている。行動経済学などがそのよい例で、バブルを作り出した群集心理などは進化に根ざすものである可能性がある。
マルサス(Thomas Malthus)の『人口論』("An Essay on the Principle of Population")を読んで、ダーウィンとウォレス(Alfred Russell Wallace)は自然淘汰(natural selection)のアイディアにたどり着いた。そしてその意味するところが当時の科学観・宗教観からかけ離れたものであり、またそれに挑戦するものであったからこそ、ダーウィンは『種の起源』の刊行に慎重であったし、また発刊後も20年にわたり、徹底的な証拠集めを行った。
進化は進歩を意味せず方向性を持たないというのが通説であるが、自然淘汰を受け入れていたとしても、この無方向性についてはなかなか一般には受け入れられていない。グールド(Stephen Jay Gould)は、進化には方向性はなく、環境の偶然の変化に適応するだけであるとする。それに対して、コンウェイ・モリス(Simon Conway-Morris)は偶然の環境に進化が左右される見方に反対している一人であり、進化は再現可能だという立場をとる。異なるグループの集団が別の環境で同じような形に進化する事例、いわゆる「収斂進化(convergent evolution)」を研究することにより、コンウェイ・モリスは進化が成功するには複雑さと知的さとを志向する二つの道があるとした。そしてダーウィン自身も、複雑な思考や情緒が脳の単純な進化から生まれてきたことについては深く悩んでいた。
しかしながら、人間の進化が完全にランダムなものかどうか、偶然によるものか予測可能なのかということよりも、重要なことがある。人間は、自然淘汰というメカニズムを理解するところまで進化した種である。人間は自然淘汰の道を止め、生存競争を終わらせることのできる存在にさえなっている。だからこそダーウィンの考えを理解すること、ダーウィニズムを応用することがますます重要になってくる。これがダーウィン生誕200年を祝福するべき理由である。
このように The Economist 誌は記事を締め括っている。進化論について、この記事に書かれている内容くらいは知っていることを、欧米知識人の教養として求められているのだろう。
ここで取り上げられた「自然淘汰は偶然か?」という命題について、『利己的な遺伝子』のリチャード・ドーキンスが自らの主張を展開する本が『盲目の時計職人』
であり、さらに宗教へ挑戦したのが『神は妄想である―宗教との決別』
である。
次に続く…。