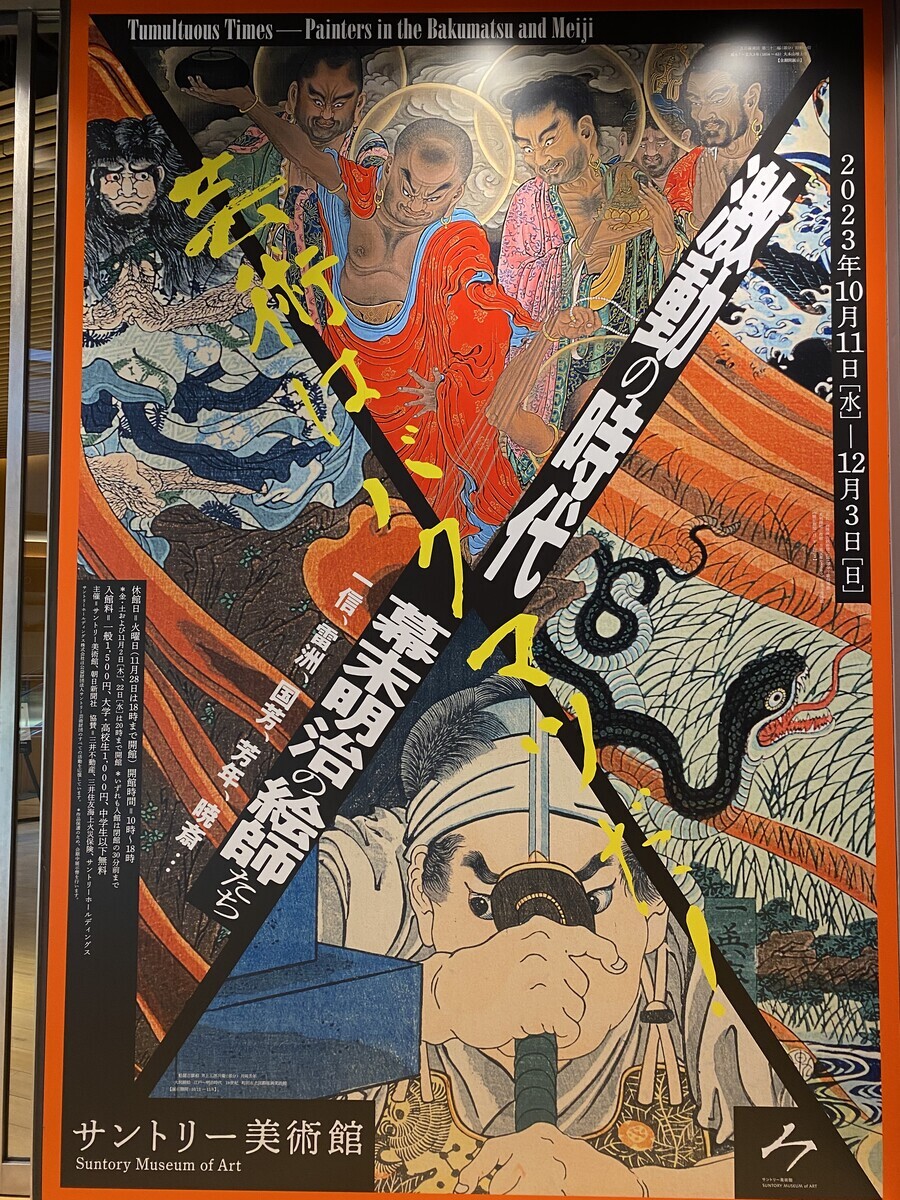出光美術館で江戸時代の美術を楽しんだ後は、ADRIFT by David Myers にて美味しいランチ。食後は静嘉堂文庫美術館(通称:静嘉堂@丸の内)へ向かう。
www.seikado.or.jp
adrift-tokyo.owst.jp
実は先日、銀座の割烹「ちくぜん」のおかみさんから招待券を分けていただいたのである。静嘉堂@丸の内が開館したのはちょうど1年前。それ以来の訪問になる。
muranaga.hatenablog.com
muranaga.hatenablog.com

開催中の展覧会は、「開館1周年記念特別展 二つの頂 ― 宋磁と清朝官窯」である。やきもの・陶磁器については、まったく知識がないが(そもそも陶器と磁器の違いを知らなかったりする)、曜変天目が南宋時代(12 - 13世紀)の磁器であることは知っている。そして世界に三つしかない曜変天目は、すべて日本にあり、三つとも国宝に指定されている。その中の一つ、稲葉天目と1年ぶりに再会することになる。
otonayaki.com
展覧会のサイト・チラシから概要を引用する:
8000年を超える悠久の歴史をもち、陶芸技術の粋を極めた中国陶磁。その歴史上、二つの頂点といえるのが、宋代(960~1279)の陶磁器と清朝(1616~1912)の官窯磁器です。
商工業や各種技術が発達した宋代の中国では、各地で青磁や白磁、黒釉など多種多様で洗練された陶磁器が生み出されました。それらは後世「宋磁」と称えられ、「古典」として現代にまで影響を与え続けています。
また最後の王朝・清朝では、磁器の都・景徳鎮に宮廷用の陶磁器を焼造する政府直営の工房=官窯が設置され、最高の技術と材料をもって皇帝のためのやきものが作られました。
清朝最盛期、康煕・雍正・乾隆の三代(1662~1795)の皇帝たちは、陶磁器への関心が高く、官窯に督陶官が派遣され、技術・意匠の両面で究極ともいうべき作品が次々と生み出されました。
静嘉堂所蔵の清朝官窯磁器には、岩﨑彌之助(三菱第2代社長、1851~1908)が明治20年代という早い段階で蒐集した作品が含まれています。また20世紀初頭には彌之助の嗣子・小彌太(三菱第4代社長、1879~1945)により、日本伝世の宋磁の優品に加え、新出の宋磁や清朝官窯の名品が蒐集され、世界有数の質を誇る中国陶磁コレクションが形成されました。
本展では、南宋官窯をはじめとする静嘉堂の宋磁の名品と、清朝官窯磁器から青花・五彩・粉彩・単色釉の優品を精選し展示します。

世界でも圧倒的な中国陶磁。その二つの頂が宋磁と清の官窯(景徳鎮)ということになるらしい。
手元には出川直樹『やきもの鑑定入門』という本がある。 40年前に出版された古い本だが、改めてこの本で陶磁の歴史・知識を学びつつ、展覧会を振り返っていこう。
中国の陶芸は唐代に発展し、青磁・白磁・黒釉の磁器が各地で焼かれた。宋代に入るとそれは最高潮に達する。
今回の展覧会でも、宋の青磁・白磁のシンプルな美しさに惹かれる。
青磁は陶土に含まれる鉄分を還元炎焼成(不完全燃焼)することによる酸化第一鉄の色。少しでも酸化炎が出ると黄濁してしまうらしい。完璧さを求めた中国の青磁が最盛を迎えたのが宋代ということになる。元以降は中国文化が衰退し、青磁の品質も落ちていく。
一方、白磁は公用や儀式用に脈々と生産されてきた。宋代では定窯の白磁、景徳鎮の青白磁が著名で、元以降は青白磁・白磁とも景徳鎮がその産出の中心になる。白磁は、白色の胎土に透明・半透明の釉がかけられ高温で焼かれたもの。土に鉄分などの不純物が少ないと白色になる。景徳鎮には高嶺山からとれるカオリン(高嶺土)があり、焼かれるとガラス質となる。
そして黒釉(天目釉)の磁器も宋代に最盛を迎える。この黒も鉄の色である。建窯(福建省)で作られた黒釉の茶碗。艶のある漆黒がひときわ美しい。窯の中で変化する、すなわち「窯変」を起こしたものが、油滴のように見えるのが油滴天目。そして夜空に浮かぶ星のように見えるのが曜変天目である(「曜変」は「窯変」から来ている。「曜」は光り輝く・星などの意味がある)。

曜変天目は、黒い釉面に大小の結晶が浮かび、その周りにぼかした状態の虹彩を持つ(出川直樹『やきもの鑑定入門』)。展覧会の説明によると、この何とも言えない美しい色は、CD やシャボン玉と同じような構造色だそうである。
白磁に藍色の絵の青花磁器(日本では染付磁器という)は、元朝末期に景徳鎮で完成し、以後、明代に主流となる。お馴染みの磁器は、コバルトの青によるものである。清朝にその高度な技巧を究めたが、その頃からさまざまな色釉や粉彩などの色絵に、主役の座を奪われていく。
釉薬をかけて一度焼いた陶磁器に色絵具で絵付をして、もう一度焼く二度焼きの方法で作られたのが色絵である。宋・明代の赤絵、淡い緑青色(剥きたての豆を思わせる)を主として黄・赤・紫などが加えられた豆彩、濃厚な五彩などがある。景徳鎮の官窯では、青花文様を下地にして上絵を加える青花の装飾が発展していく。
今回の展覧会でも、三彩・五彩・青花・豆彩が数多く展示されている。
 素三彩
素三彩
 五彩・青花
五彩・青花
 素三彩・豆彩
素三彩・豆彩
清朝の景徳鎮官窯の色絵磁器の特色は、精緻な白磁と豊富な色料、そして粉彩と呼ばれている新しい色絵技法である。粉彩とは白磁の釉肌に、石英砂に鉛粉を混ぜた琺瑯(ほうろう)料を塗り、それを下地として彩色した色絵のことである。光沢のある釉肌とちがい、吸着力のある琺瑯質の下地の上に描くので、きわめて微妙な濃淡や中間色を表現することが可能となった。
清の皇帝たちの時代に作られた粉彩の精細な絵が美しい。
 粉彩菊蝶図盤「大清雍正年製」銘
粉彩菊蝶図盤「大清雍正年製」銘
 粉彩百鹿図壺「大清乾隆年製」銘
粉彩百鹿図壺「大清乾隆年製」銘
今回、「特別展 二つの頂 ― 宋磁と清朝官窯」を見て、さらに出川直樹『やきもの鑑定入門』に目を通して、中国の宋代から清代までの陶磁の歴史を学ぶことができた。還暦過ぎて初めて、陶磁器の世界の一端を垣間見た気がしている。ただし 40年も前に書かれた本に基づく知識なので、最近の本でアップデートしておく必要があるかもしれない。
日本の陶磁(やきもの)に目を転じよう。
時代別と分野別を組み合わせた多視点の記述が特徴的な、古田亮『教養の日本美術史』の「第10章 やきものの日本美術」によると、豊臣秀吉の朝鮮出兵により多くの陶工が渡来した。そして肥前・有田の地で磁器焼成に成功したのは 1610年頃だと言う。6世紀後半に中国で初めて磁器(白磁)が完成して以来、なんと1000年余りの年月を経てのことであった。
それからわずか半世紀の間に、日本の磁器は飛躍的に発展する。ちょうど明から清へ移る内乱の時代、中国からの磁器の輸入が激減する間に、肥前窯は技術革新に努め、一気に国内需要拡大を成功させ、色絵磁器を創成した。初代柿右衛門が、色絵の焼成に成功していたのは 1647年とされる。初期の景徳鎮磁器を模倣する段階から、日本特有の優雅なスタイルへ発展し、柿右衛門様式として結実する。
柿右衛門様式を讃える言葉としてよく使われるのが「余白の美」。これはまさに、この日の午前中に出光美術館にて見た、狩野探幽が提唱した「つまらない」絵画のスタイルである。
muranaga.hatenablog.com
磁器の技術を獲得する前の日本は、陶器と焼締めの時代であった。わずか半世紀の間に技術革新を遂げた肥前窯も凄いが、それと同時期に、磁器の技術や素材が手に入れられない京都の地で、野々村仁清や尾形乾山は、陶土と釉薬を探究し、優雅で洒脱な造形を作っていたのだと思うと、感慨深い。
muranaga.hatenablog.com